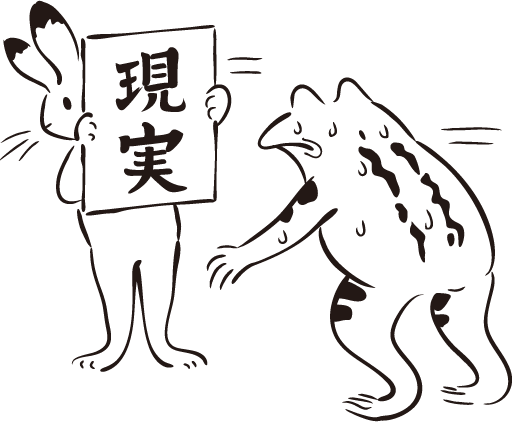
前任者や先輩が置いていった大量のモノにうんざり
あなただったらどうしますか?
選択肢は2つあります。
見て見ぬふりをして別のラボに移るか、転職する
自分にできることをする
このどちらかです。
使いにくい場所で我慢して過ごす生活を選ぶのか、それとも行動を起こすのか?
どちらがあなたにとってその後のメリットがあると思うかで決まるでしょう。
今回の記事は、どうしたらいいかわからないと悩んでいる方に伝えたいことを書いて見ます。(私も悩んでたので)
1. そもそもラボの整理整頓はどうしてやるのか
2. 整理整頓のやり方いろいろ
2-1. 気になるところをまず書きしてみる
2-2. 整理をラボの祭りに
2-3. 自分の周りを少しずつ
3. 乗ってこない人への接し方
まとめ
1. そもそもラボの整理整頓はどうしてやるのか
はたから見たら物置にしか見えないようなラボでも、研究成果をあげ続けていれば、どこからも文句はこないでしょう。
でも、最近の研究は複数の人間が集まってやるのが普通です。複数の人間が働く職場ではどうしても秩序が必要で、それは工場であろうと美容室であろうラボであろうと同じです。もし天才研究者が、共用のものを所定の位置に戻さなかったり、自分の実験にしか使わないものをそこら中に散らかしていたら、凡人研究者は困ります(指摘しにくいから余計に)。
整理も整頓も収納も、研究成果をあげやすい環境を作るために最も簡単にできる有効な手段だからやるんです。(研究自体は思い通りになるわけないですし、人間を整理したり思い通りに動かすのはもっともっと難しいです。)
しかし、ラボを主宰する研究者(PI) がこれを意識していないと、様々な問題が生じてくる可能性があります。例えば 事故、ルール違反、実験の遅延、不適切なデータの管理、人間関係の悪化 です。
さらに、散らかっている・汚い・管理の行き届かないラボというのは、人を遠ざける原因になります。
もし大学院への入学を考えている学生さんや、共同研究先を探している企業からのお客さんが訪問してきたとしましょう。
あなたのラボに毎日通って研究したいか?
共同研究先としてどうか?
就職先としてどうか?
ということを考えたとしましょう。そのとき、ダントツに魅力的な研究をしていたり、尊敬する研究者がいる場合を除いて、やはり見た目というのは判断材料の一つではないでしょうか。
だから、優秀な人材を集めたり、共同研究先といい関係を作っていく上でも、整理整頓は重要なのです。
(実際、私が企業に勤めていたときに共同研究の候補先を何件か回りましたが、上司の判断基準の一つが ”ラボがきれいかどうか” でした。これ、本当の話です。)
2. 整理整頓のやり方いろいろ
すでにモノが多く、誰が何を使っているのか、床の上に放置されているように見えるけれど捨てていいものかわからない、どこから手をつけたらいいかわからない、という場合が多いのではないかと思います。こういう状態だと、いきなり整理しようとしてもムリです。
2-1. 気になるところをまず書き出してみる
まずは気になるところを書き出して見ます。書き出すだけです。
- 捨てても問題なさそうに見えるもの
- 誰に判断してもらえばいいかはっきりしているもの
- 誰のものか不明なもの
- 誰も使っていなさそうなもの
- 用途が不明なもの
リストアップだけしておき、然るべき人(ラボのリーダー、あるいは管理を任されている立場の人)に相談します。理解のあるリーダーなら、多くを説明しなくてもわかってくれます。気づいてはいたけれど、時間がなくてやれなかった、という返事が返ってくることもあります。
逆に、ここで全く取り合ってもらえないとその先はかなり厳しい。リーダーとしては、なるべく実験の手を止めて欲しくないという人もいますし、時期的に(科研費申請の締め切りとか)人手と時間を割けないので協力を得られないこともあります。その場合は自分の使う範囲内の限定箇所をちょっとずつ整理する方法をとりましょう。まず自分の実験台の上・引き出し・実験台の棚から始めるのがいいでしょう。
2-2. 整理をラボの祭りにしてしまう
一気に進めるなら整理整頓を年末大掃除や年度末棚卸しイベントにしてしまうという手もあります。実際、これで整理整頓コンペティションをやり、忘年会で表彰式をやったことがあります。(幹事さんには大層喜ばれました。)
ただ、イベントでできることは一過性で、限定的です。
習慣化していくためには各自が不要品の見直しを繰り返す、モノを戻しやすい収納方法に変えていく、卒業時に引き継ぎをルール化することが必要です。
これができればいいのですが、システムを作るところまで一足飛びには進まないのが普通なので、あまり焦らないように。
2-3. 自分の周りを少しずつ
自分の場所を整理整頓してスッキリした顔をしていると、だんだん、周りの人のあなたをみる目が変わってきます。
“整理整頓上手な人” として認識されるようになったらしめたもの。徐々に範囲を拡大していくチャンスがやってきます。
捨てずにどこかを変えたら使いやすくなる、実験をしやすくなる、使いやすくなる、という小さいところから始めます。そして、他の人に ”使いやすくなったな” という効果を感じてもらえるような、アイデアを試してみましょう。
共用文房具の引き出しでもなんでもいいのです。ごちゃごちゃに入っていて、何かを探しにくいと感じるところを、どうしたら使いやすくできるか考えて見ます。
例えばラベルが不十分なところにラベルを貼ります。引き出しに入った試薬の奥の方が見づらいのであれば、奥の方に仕切りや箱を置いて、瓶が入らないようにします(スペースに余裕がないとできませんが)。
ここで気をつけたいのは、明らかなゴミ以外はいきなりモノを捨てないこと。
捨ててもいいかも、と思うものは他の人の目につくところにメモとともに一定期間展示して、展示期間が過ぎたら捨てるという、プチ展示会をやります。
それから、モノを移動するときは、とにかく張り紙したり、事前にアナウンスしておくことです。勝手にやってはいけません。
3. 乗ってこない人への接し方
イベント企画にする場合でも、プロジェクトチームを作る場合でも、あまり変化を好まない人、整理や片付けが嫌いな人、関心がない人、は乗ってきません。それに時間や心に余裕がない人に整理の話をしても聞いてもらえません。無理強いすると衝突したり、拒絶反応がでます。
これはお互いに疲れますし自分にもストレスがかかります。人間関係がわるくなります。だから強制しないこと。やる気になった人だけ、気持ちよく賛成してくれる人とだけ一緒にやりましょう。
そうでない人はおいおい話してみることにして、無理強いしないのが肝心です。
勉強熱心な人にありがちな間違いは、整理収納について得た知識をすぐに他人のものに適用しようとしたり、聞きなれない専門用語を使って理論を振りかざす(あなたにはそういう意識はなくても、他の人からはそう見える)ことです。
大多数の研究者は、片付けた方がいいのはわかっているけれどそういうことを人から指摘されたくないし、ましてや勝手にやられると腹を立てます。たとえあなたのおかげでラボが使いやすくなったとしても、他の人には感謝されるどころか、反感を買うということになってしまうことも起こりかねないので注意しましょう。
まとめ
ものが多くて使いにくくなっているラボでは、コミュニケーションがうまくとれていなかったり、人間関係のトラブルを抱えていたり、PIが問題に気づいていない、対処できていない、見て見ぬ振りをしている、といった原因が潜んでいることもあります。そういう場合、残念ながら自力で問題を解決するのは不可能です。
微妙な問題に関わることは余計なストレスを抱えることになります。あなたがPIでないのであれば、そっと様子を見守る方がいいでしょう。
それでもできることはあります。
周囲の人にも学習の機会を作るという名目で、外部講師の講座やセミナーを聞いてもらうことです。これならラボの人が誰も傷つかず、整理整頓の雰囲気やきっかけ作りをソフトに後押しすることができるのです。
