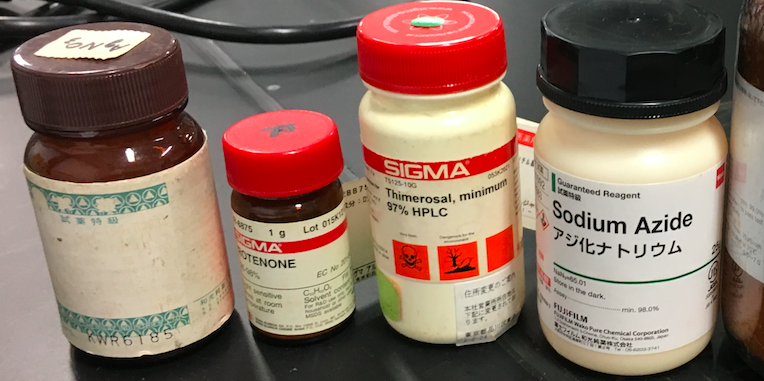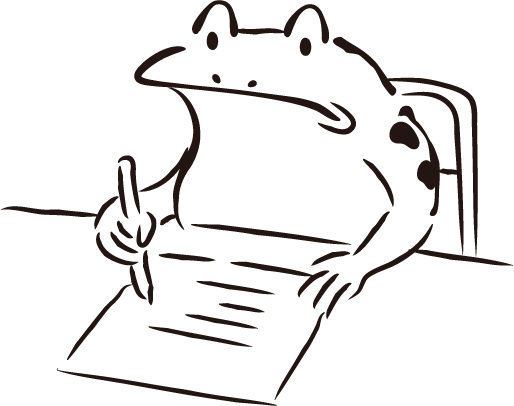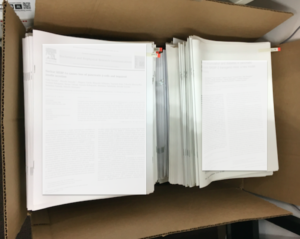研究所や大学にいるみなさん、電子データファイル、さがしにくくて困っていませんか?もし困ったことが起きているならば、デジタルファイルの保存方法や命名ルールを見直してみましょう。
困ったことの例としては
・過去のデータが探せない
・検索キーワードでヒットしない(命名法がバラバラだから)
・ヒットしすぎて絞りこみにくい
・情報共有がうまくいってない(属人的管理)
・保存の階層が深くなりすぎ
・分類が複雑でわかりにくい
・自分の呼び方と人の呼び方の違いによる用語の不統一
何のルールもない部署やラボでは、電子データや電子ノートのタイトルを各人が『適当』につけている。属人的な管理方法や命名をそのままにしておくことは、研究にとっての時間的・経済的損失につながります。
そしてなにより、「探し出せないことによる精神的なストレス」があるでしょう。
解決のヒントがほしい、具体的にどんなファイル名の付け方をしたらいいのか、などアドバイスが必要な方は30分のオンラインコンサルティングをしていますのでお問合せください。